![]() のカンも入っていて、異常な牌の偏りを見せている今局。
のカンも入っていて、異常な牌の偏りを見せている今局。
あわや四暗刻か? …という場面だったが、

河に2枚目の![]() が顔を出して止むなくポンしてテンパイ。
が顔を出して止むなくポンしてテンパイ。
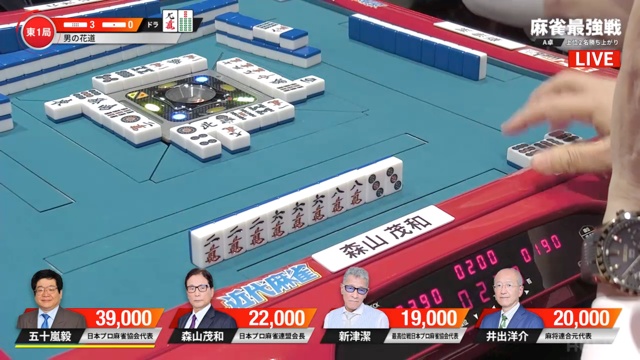
そして、新津にもテンパイが入った。

フリテンの![]() を引き戻してカン
を引き戻してカン![]() 待ちでリーチとした。
待ちでリーチとした。
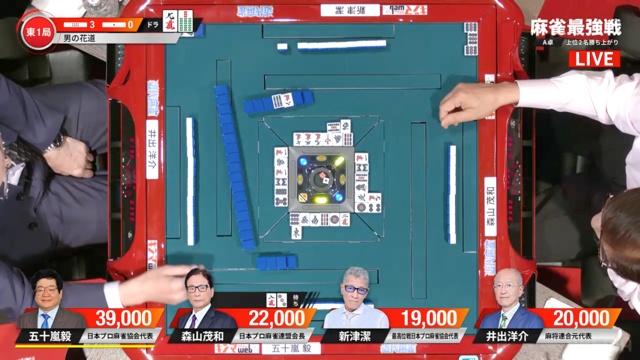
こうして仕掛けとリーチに挟まれた場合、現代の麻雀では「行く」か「オリる」かの2択で態度をはっきりさせる打ち手が多いかと思う。
特に、持ち点が多い五十嵐の立場では、頭を低くして嵐が過ぎ去るのを待つのがクレバーな選択と言われるのだろう。
現に五十嵐はこのリーチの一発目に、

![]() のトイツ落としで回ってみせるのだが、これは「オリた」わけではなくて「受けた」という表現がしっくりくるように思う。
のトイツ落としで回ってみせるのだが、これは「オリた」わけではなくて「受けた」という表現がしっくりくるように思う。
私の勝手な思い込みなら不明を恥じる次第だが、昭和の時代の麻雀を知っている打ち手は「先々で手を詰まらせず、可能な限り和了への道を模索する」という茨の道を、いとも容易く突き進んでしまう強さを持っている気がするのだ。
五十嵐が昔から「鉄壁の守備力」が持ち味と称されるのは、単にベタベタとオリているわけではなく「簡単に降参しない」ためではないかと私は思う。

ビュン、と音がするような速度で森山が無筋の牌を押していく。

森山が切り拓いた道を手がかりに、井出が手を進めていく。

森山がドラすらも力強く切り飛ばす。

その姿を見とめて、新津がわずかに微笑んだ。
牌を介して、そこでは会話が成立しているかのようだった。
白熱する二人のやりとりをよそに、井出は至って冷静な面持ち。
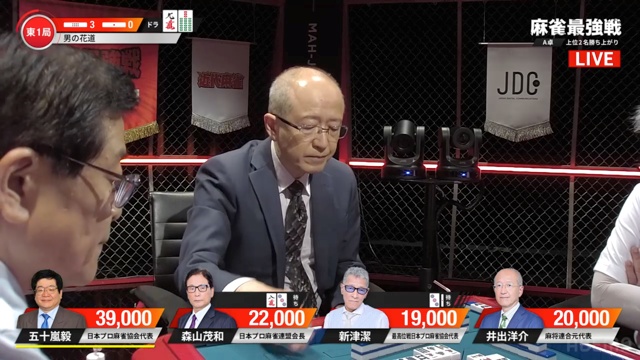
「今は、まだ。」

受け駒の![]() を落として一旦場を預ける。
を落として一旦場を預ける。
そして、二人の和了牌である![]() を吸収した五十嵐。
を吸収した五十嵐。

森山の![]() を叩いて全面戦争とはいかず、こちらも二人の攻めに徹底した受け姿勢。
を叩いて全面戦争とはいかず、こちらも二人の攻めに徹底した受け姿勢。
ドラの![]() を1枚外して受ける。
を1枚外して受ける。
ここまできたら、あとは二人のめくり合い…
となるのだったら、私はわざわざ観戦記に取り上げない。
ここからが素晴らしかった。

一旦受けた井出の手に、急所のペン![]() が埋まった。
が埋まった。
これでマンズ1枚を勝負するイーシャンテン。
そして、五十嵐。

うまくカン![]() を引き入れてこちらもイーシャンテン。
を引き入れてこちらもイーシャンテン。
さらに、井出が![]() を吸収し、新津が今切ったばかりの
を吸収し、新津が今切ったばかりの![]() を合わせると、五十嵐にチーテンが入った。
を合わせると、五十嵐にチーテンが入った。

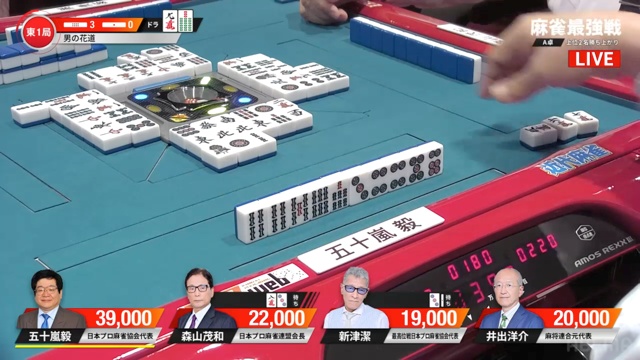
そして、最後は井出。

今度は五十嵐のロン牌である![]() を押さえ込み、こちらもテンパイ。
を押さえ込み、こちらもテンパイ。
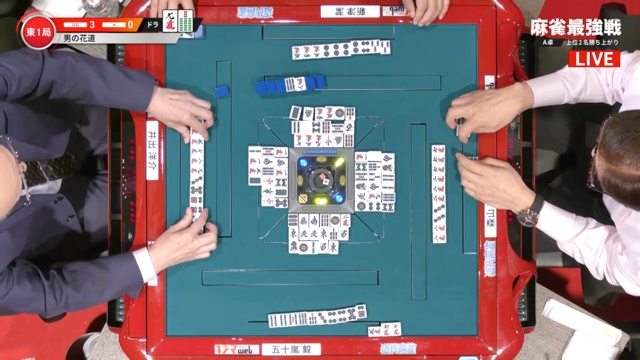
全員テンパイで流局。
このコロシアムだけ、まるで昭和に戻ったかのような… そんな見応えある一局だった。
この局には、現代麻雀に対する指摘が多く含まれているような気がした。
リーチに怯むな。
簡単にメンツから現物を抜きうつな。
そして、最後まで諦めるな。
親父たちの背中が、言葉よりも鮮やかに教えてくれたような気がしてならない。













