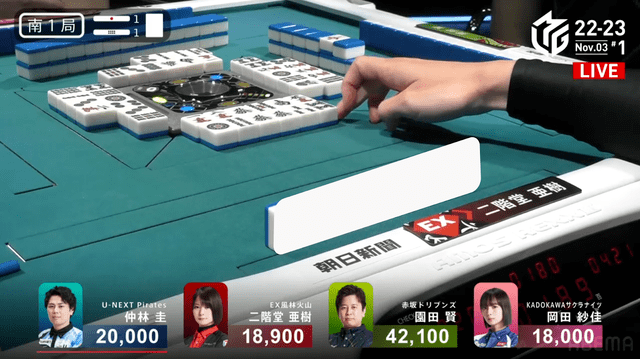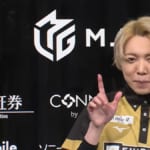対面の仲林がすでに2副露。そこに上家の亜樹が![]() を切ってきている。
を切ってきている。
確かにダマにしておけば、下家の岡田が次に![]() が打つ未来をはじめ、この手をかわし手として活かすことが出来る。
が打つ未来をはじめ、この手をかわし手として活かすことが出来る。
ただ、まだ東4局では40100点が安全圏とは言えない。また、リーチをしたとしても他家が勝負してくれる可能性もある。
ここは、さらにリードを広げるための「決め手」としてこのハンドを使うことを決断し、

園田はリーチを打った。
我々が見ている「神視点」では、

このように、仲林も亜樹もそこまでの形ではないことが分かるので、「何を考えてるんだろう?」と感じた方も多いだろう。
このように選手が小考した場合や、何か平面効率と違った打牌をした場合には、理由を探すのがオススメだ。そうすれば、麻雀観戦にも自身の麻雀にも深みが出るように思う。
このリーチは、

園田の一人テンパイで流局。中押しのアガリとはならなかったが、さらなる点差をつけて南場に突入だ。
南1局1本場に、亜樹が動いた。
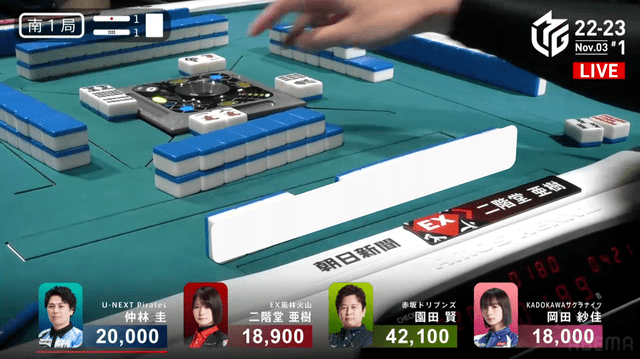
南家の亜樹は、3巡目にカン![]() をチー。打
をチー。打![]() とした。
とした。
懐の深い亜樹が早めに動いたとあって、場に緊張感が走る。
さらに、
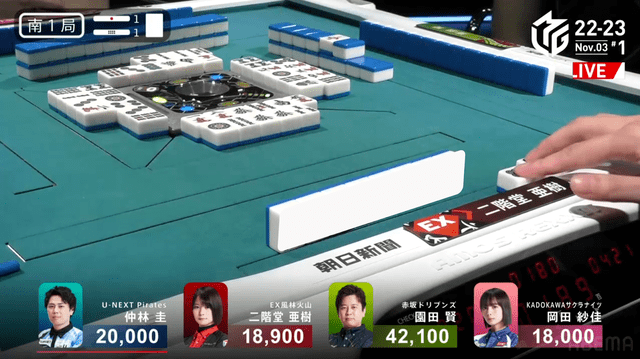
亜樹は終盤に差し掛かるところで![]() をチー。
をチー。
その瞬間、

全員の打牌がスローになった。
亜樹の手を読んで、自分がどう立ち回るかを整理していたのだ。

まず園田視点では、
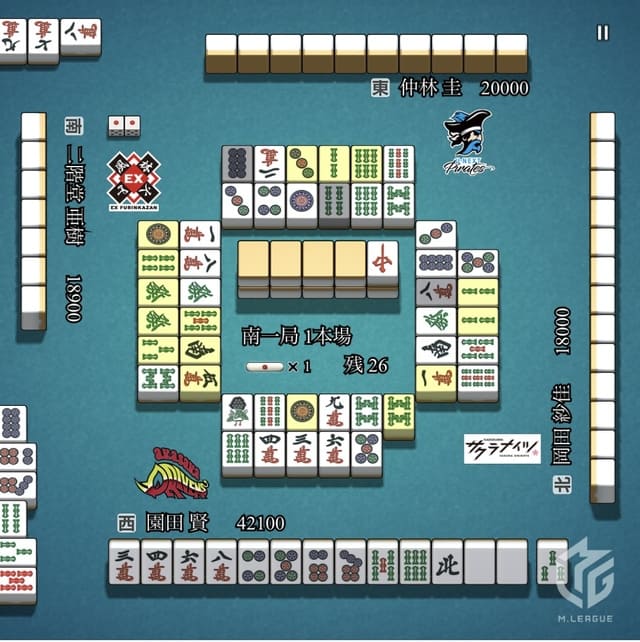
ドラの![]() が2枚あるのが大きい。亜樹が
が2枚あるのが大きい。亜樹が![]() アンコではないと分かるからだ。
アンコではないと分かるからだ。
それもあって、亜樹の仕掛けはタンヤオの可能性がかなり高いように見える。亜樹の打点が安いのならば、打って局を流してもいいという考えもあったそうだ。
ここでは、手出し![]() があったとはいえ亜樹の仕掛けに
があったとはいえ亜樹の仕掛けに![]()
![]() をゴリ押ししている仲林に、マンズや字牌は打ちづらい。
をゴリ押ししている仲林に、マンズや字牌は打ちづらい。
一旦打![]() として、そのあとは様子を見ながらソウズを打つことになりそうである。
として、そのあとは様子を見ながらソウズを打つことになりそうである。
しばし考えた後、園田は![]() を切った。
を切った。
続いて、

岡田視点では、
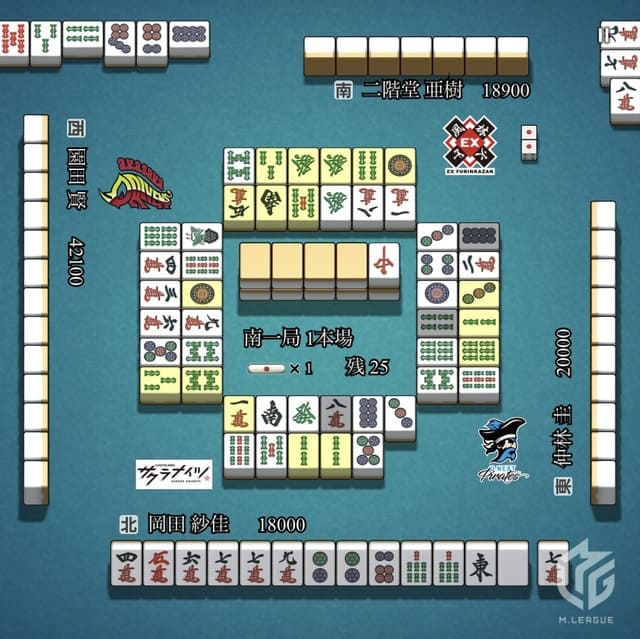 ここはまず、亜樹の
ここはまず、亜樹の![]() アンコの可能性を考えないといけないから大変だ。
アンコの可能性を考えないといけないから大変だ。
また、これは全員に言えることだが、亜樹の最後手出し![]() は手牌に関連していたとは限らない。安全度の高い牌として残していた可能性があるからだ。待ちを
は手牌に関連していたとは限らない。安全度の高い牌として残していた可能性があるからだ。待ちを![]() 近辺と絞ることはまだできない。
近辺と絞ることはまだできない。
何を切るか。
仲林が下家にいることも含めて、マンズと字牌は打牌候補から消去。![]() も亜樹に
も亜樹に![]()
![]() 待ちがあるので除いて、切るなら
待ちがあるので除いて、切るなら![]() か
か![]() 。
。
![]() が当たると仮定すると、
が当たると仮定すると、![]()
![]() と持っていたところからの
と持っていたところからの![]() 単騎待ちがあるが、それなら仲林が切った
単騎待ちがあるが、それなら仲林が切った![]() は鳴いていそうである。
は鳴いていそうである。![]()
![]()
![]() でもほぼ同様。役牌が絡むシャンポンで
でもほぼ同様。役牌が絡むシャンポンで![]()
![]()
![]()
![]()
![]() のような形でも
のような形でも![]() は当たらない。
は当たらない。
一方の![]() に関しては、亜樹は
に関しては、亜樹は![]() を鳴いていないので、
を鳴いていないので、![]()
![]()
![]()
![]() からの
からの![]() チー
チー![]()
![]() 待ちは薄そうだ。
待ちは薄そうだ。![]() もかなり通りそうではあるが、
もかなり通りそうではあるが、![]()
![]()
![]()
![]() や
や![]()
![]()
![]()
![]() からの
からの![]() チーは組み合わせとして残っている。
チーは組み合わせとして残っている。
よって、ここで岡田は打![]() としたのだろう。
としたのだろう。
最後に、
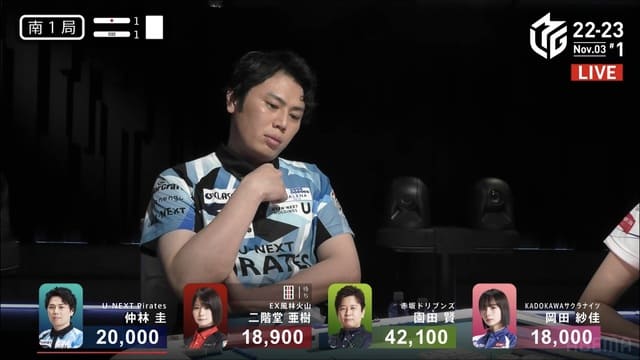
仲林視点では、

ここも亜樹が![]() アンコであるパターンを含めて考えないといけないから大変だ。もちろんタンヤオもある。
アンコであるパターンを含めて考えないといけないから大変だ。もちろんタンヤオもある。
切るのは先ほど鳴かれなかった![]() になるだろうが、
になるだろうが、![]() はもちろん
はもちろん![]() や
や![]() は打てない。よって、ここから
は打てない。よって、ここから![]() や
や![]() を鳴くことは控えておこうか、ということも含めて思考整理をしていたのではないだろうか。
を鳴くことは控えておこうか、ということも含めて思考整理をしていたのではないだろうか。
仲林は、打![]() とした。
とした。
亜樹の手は、

このような![]() アンコでの仕掛けであった。ここらフリテンの
アンコでの仕掛けであった。ここらフリテンの![]() を切ったが、
を切ったが、![]() がもうないので、亜樹は次巡に打
がもうないので、亜樹は次巡に打![]() として単騎を変えていった。
として単騎を変えていった。
この後、他の選手は亜樹の![]() →
→![]() の切り順から、タンヤオではなく役牌絡みの手が濃厚(タンヤオならここまで
の切り順から、タンヤオではなく役牌絡みの手が濃厚(タンヤオならここまで![]() が残っているのがおかしい)、さらには単騎待ちを転がしている、と読んでいった。
が残っているのがおかしい)、さらには単騎待ちを転がしている、と読んでいった。
こういった読み合いによる攻防もMリーグの醍醐味の一つだ。
私が他に切る牌はなかったかな、と感じたのが、
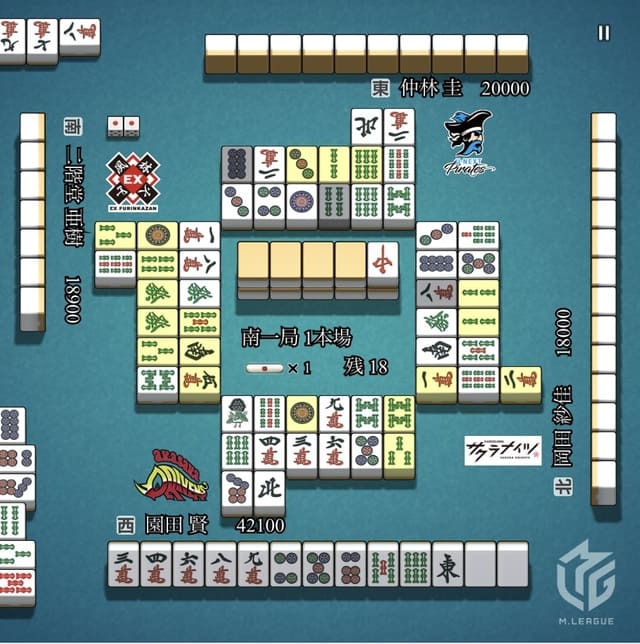
園田がここで打![]() としたシーンである。
としたシーンである。
先に仲林が通しているが、それは亜樹が打![]() とする前のことだ。もちろん仲林の手に残っていて、この土壇場で打ち出す
とする前のことだ。もちろん仲林の手に残っていて、この土壇場で打ち出す![]() が1枚であるケースは少ないだろう。アンコからの切り出しなら当たらないし、2枚落としだとしたら、亜樹が前の手番で
が1枚であるケースは少ないだろう。アンコからの切り出しなら当たらないし、2枚落としだとしたら、亜樹が前の手番で![]() を引いてきたときしか放銃することはない。
を引いてきたときしか放銃することはない。
ただ、僅かな可能性とはいえ当たり得る牌だ。園田視点からは![]() アンコがないし、亜樹がアガると局が進むとはいえ、
アンコがないし、亜樹がアガると局が進むとはいえ、![]() アンコの赤赤の手に打ち込む可能性は0ではなく、それは歓迎でないだろう。
アンコの赤赤の手に打ち込む可能性は0ではなく、それは歓迎でないだろう。