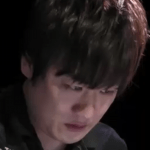中央線アンダードッグ
長村大
第39話
ひとまず会社を休むことになった。
仕事がキツいと思ったことはある、365日、ほとんど仕事と休みの区別ない生活を何年かしているのだ。給料だって安い。
だが嫌だと思ったことはなかったし、基本的には楽しんでいたはず、なのだが、いったん休んでみるとやはり少し楽になった。
思えば、知らず知らず気を張っていたのだろう。バベルのメンバーは友人でもあったが、それと同時に仕事仲間である。純粋な友人関係とは少し違う。プライベートもクソもない、四十六時中顔を合わせているのだ、ある種の特別な関係であった。そもそも、おれは純粋な友人というものをほとんど持ち合わせていなかった。
NPMAでもそうであった。元々馴れ合うのが苦手であり、馴れ合っているやつらを軽蔑していた。わざわざ日本麻雀プロ協会を分裂させる一端を担った以上、新しい場所で同じことを繰り返すなんてバカなことはしたくない。人が集まってワイワイするような場所をことさらに嫌うようになっていたし、あえて露悪的に振舞っていた部分もあった。
最近になって、久しぶりに当時の知り合いに会うと「昔の小山田さんは怖かった」みたいな話をよく聞かされる。その度に半笑いで「そんなことないでしょ」などとヘラヘラしているが、もちろん心当たりはある。あるいは当時、おれに厳しい言葉を浴びせられたり、バカにされたりして腹を立てた人も少なからずいるだろう。今更遅いのは重々承知だが、自分で思い当たる節がある相手に会った折には謝罪していくようにしている。いい人ぶるつもりは毛頭ない、だが申し訳ないと思っているのは本当だ、どう考えてもおれが悪い話なのだ。
おれには謝らなければいけない相手がたくさんいる。
少し話が逸れた。
とはいえ、少し会社を休んだからといって急激に気分が良くなったわけでもない。薬のおかげもあろう、朝のエネルギー不足はゆっくりと回復しているように思えたが、暗くなってから訪れる希死念慮や落ち込みはあまり変化がなかった。学校やらなにやら、今まで投げ出してきたいろんなこと──投げ出さなかったことなどないのだが──を思い出し、結局バベルも同じように投げ出してしまったことを思う。何度同じことを繰り返すのか、なんでちゃんとやれないのか。
打牌をしたおれの指が河から離れた直後、「あ、その![]() ポン!」とトイメンのおっさんが言った。しかしおれが切ったのは
ポン!」とトイメンのおっさんが言った。しかしおれが切ったのは![]() であり、
であり、![]() は上家の捨て牌の端に並んでいる。
は上家の捨て牌の端に並んでいる。
「さすがに遅すぎるわな、すまん」
自ら空ポンの千点罰符を放り投げたおっさんの右手は、小指が少し短い。
高円寺、通称「ピンサロ通り」の入口ちかくに、「フリーダム」という雀荘があった。名は体を表す、ではないが、フリーダムな客層というか、要はすぐ隣に稼業者の事務所があり、そこの人間が経営している店だ。客もその筋の人間と商店街のおっさん風ばかりだったが、レートはいたって普通のピンの東南戦であった。古き良き雀荘の風情である。
「お!」
なにかをツモった小指のおっさんがわかりやすく表情をほころばせて「よっしゃ、リーチ!」と言って二本目の千点棒を卓の中央に放った。鳴き忘れた![]() が暗刻になったに違いない。
が暗刻になったに違いない。
「一発ツモ!」
人を殴るときと同じ強さで、卓の縁に牌を叩きつけるおっさん。
お見事、メンホン四暗刻である。
「気付くのが遅いほうが、逆に良いこともあるってことだな」
嬉しそうに呟くおっさんの言葉にはしかし、嫌味はこれっぽっちもなかった。
店を出て、小説のタイトルにもなった有名な商店街のあたりをあてもなくブラブラしていたところ、同級生とバタリと出くわした。スギオカという女の子で、おれと同じく小学校から大学までエスカレーターに乗ったやつだった。今はフリーランスのカメラマンをやっているはずだ。
いかにも高円寺、といった感じの民族衣装風とモードを組み合わせたようなよくわからない恰好の彼女が、おれを認識して「あれ、小山田! 久しぶり!」と声をかけてくれた。大学以来、5~6年ぶりだろうか。そういえば実家が高円寺だと言っていたような記憶がある。
ちょっと飲みに行こうか、という話になり、沖縄料理の店に行くことにした。ベタな選択である。
スギオカとはすごく仲が良い、というわけでもなかった。小学校から一緒だが、少なくとも高校まではほとんど話したこともなかった。大学に入ってから音楽やら小説の話が意外と合うことを知り、たまに飲みに行ったりする程度の付き合いであった。
「久しぶりだね、小山田は今なにやってるの?」
ビールのグラスを合わせて、スギオカが聞く。
「相変わらず書き物仕事とかだけど、今は体調崩してちょっと休んでるところなんだよね」
「そうなんだ、まあそういうこともあるよね」
あっさりとしたもので、特に理由を聞いてくることもない。やりやすい相手なのだ。
おれやスギオカといった小学校から通っている連中は、基本的に恵まれた家庭環境であったはずだ。経済的にも余裕のある家庭で、良識ある両親の愛情を目いっぱいに受けてなに不自由なく育ってきた。特にそのまま大学まで行った者は、生涯で受験勉強というものを一度もせずに社会に出るわけで、なんというか競争心とか向上心、ガツガツすることに対して一歩引いてしまう気風があるように思う。おれ自身もそうであった。
そういう環境から、おれやスギオカのような自由業に就く者は少ない。医者や士業になる者のほうが圧倒的に多い、そういう道を選択しなかったマイノリティ同士のシンパシーもあったかもしれない。
小一時間ほど飲んで、まあ昔話だとか誰ぞ作家の話などして、解散しようとしたときであった。
「そうだ、昔小山田に本貸したよね?」
思い出した。
柳美里の「ゴールドラッシュ」という小説だ。「これの主人公が小山田に似てるんだよ」と言われ、借りたのだ。
「『ゴールドラッシュ』ね、そういえば借りっぱなしだな、今度返すよ」
「アハハ、いいよ別に。それじゃまたね!」
そう言ってスギオカは去っていった。
短い時間だったが久しぶりに友人と呼べる人間との時間が持てて、なんというか自分もそういうことができるんだ、と思って嬉しくなった。遅くはない、まだ少しは、まともな人間ぽいことができる。
「ゴールドラッシュ」がどんな話だったかまるで思い出せなかったので、家に帰って本棚やら開けてない段ボールやらかき回して見つけ出して読んでみたが、主人公の少年とおれが似ているのかどうか、自分ではよくわからなかった。
スギオカともそれ以来会っていない。「ゴールドラッシュ」の文庫本も、ずっと本棚に置きっぱなしだ。
第40話(8月21日)に続く。